現在、案件探し中ということもあり割と自由に使える時間ができました。
せっかくの空き時間なのでいろいろやろうと思い、その中でもアウトプットをもっと増やそうと思いました。
そんなわけで今回は、アウトプットを増やそうと思い至った経緯やこれからどういうことをやっていくかの決意なんかをつらつらと述べていこうと思います。
なぜ今までアウトプットを避けていたのか?
今までアウトプットらしいアウトプットはこのブログくらいでした。
更新頻度も月2回程度でとても頻繁にアウトプットしているとは言えない状態でした。
「エンジニアたるものアウトプットは積極的にすべき!」という考えの人もいるでしょう。
ごもっともな指摘ですし、何なら僕もそう思っています。
そう思っていたのにも関わらずなぜアウトプットを積極的にしていなかったのか?
以下、言い訳です。
- 仕事等で時間がなかったから
- なかなかモチベーションがわかなかったから
- クオリティの高いアウトプットを出せる自信がなかったから
- すでに誰かがアウトプットを出してるネタだったから
- 継続的にアウトプットを出すのがめんどくさいから
- 誰にも見られなかったら悲しいから
こんな感じのことを考えながら、だらだらとアウトプットをせずにいたわけです。
なぜアウトプットをしようと決意したのか?
残念ながら「○○の記事に感銘をうけて」「△△さんの発言に共感して」みたいな前向きな理由ではありません。
「このままアウトプットをせずにいると、そのうち仕事がもらえなくなるのでは!?」という危機感からアウトプットする決意に至りました。
自分で言うのもなんですが、業務を遂行する能力はけっこう自信があります。新たに関わることになったコードの理解は早い方だと思いますし、開発速度やコードの品質もそれなりのものだと自負しています。
スキルシートにはきちんとその旨記載してありますし、面談時にもしっかりアピールはしています。
今まではそれらのアピールだけでも通用していましたが、今後もそれだけで十分かはわかりません。もしかしたら全く問題ないかもしれませんが、逆にアピールが全然足りずに全く仕事がもらえないパターンもありえます。
そこでもっと説得力のあるアピール材料としてアウトプットに目を付けたわけです。
単に文章や口頭で「○○に自信があります!」というよりも、「○○に関わる機能をGithubにあげています!」「○○についてQiitaに記事出してます!」の方がより強力なアピールになるのは明らかです。僕がフリーランスを採用する立場だったとしても、スキルシートの内容や面談時の印象が同じくらいの評価の人が2人いるとしたらよりアウトプットを出している方を採用すると思います。
そんな現実を直視して「じゃあ、やるしかないか」と腹をくくってアウトプットを増やす決意をしました。
どんなアウトプットをしていくつもりか?
アウトプットを始めるとしても、いきなりあれもこれもと欲張って進めていくと力尽きるのは目に見えています。
なので今の自分にできる範囲で少しずつ始めていこうと思っています。
まず大前提として、このブログでは引き続きフリーランスやゲーム開発にまつわる話、特に考え方や心構えといった技術以外の話をする予定です。
なので上記以外の内容かつエンジニアとしてアピールになりうるもの、要するに技術的なことについてアウトプットをしていくつもりです。
それに並行してアウトプットの宣伝もすることにしました。せっかく世に出したアウトプットですから人に見てもらいたいですしね。
そんなわけで主に以下の媒体でアウトプットをしていこうと思っています。
Zenn
Zennはエンジニアが技術的なことについての知見を共有しあう媒体です。Qiitaと同じようなサービスですね。
ZennとQiitaのどちらを利用するか悩んだのですが、ChatGPTにいろいろ相談した結果、紆余曲折を経てひとまずZennを利用することにしました。
Zennには以下のような記事を出していく予定です。
- 開発中に出くわした問題とその対応策
- 自作した便利機能の紹介
- 勉強して得られた知見
実はすでにいくつか記事を出しています。
よろしければ見てやってください。

X (旧Twitter)
わざわざ説明するまでもないと思いますが、言わずと知れたSNSです。
そもそもブログと同時にやっておくべきだった気がしないでもないですが、遅ればせながらアカウントを作りました。
主に以下のような発信をしていく予定です。
- ブログやZennの記事を公開した時の宣伝
- ブログやZennの記事にするほどのボリュームがない小ネタ
- フリーランスとしての活動報告
よろしければフォローやいいねをお願いします。
アウトプットに対する考え方の変化
まだまだアウトプット初心者ですが、いくつかアウトプットについて考え方が変化したのでそれについて述べていきます。
クオリティにこだわりすぎなくて良い
アウトプットするからにはクオリティの高い内容でないと意味がないと考えていました。
「読みやすい文章、正確な情報、誰が読んでも納得できる構成じゃないといけない」みたいなかんがえでした。
しかし、よくよく世に出ているアウトプットを見ていると、失礼ながら必ずしもクオリティの高いものばかりではないことに気づきました。
誤字脱字があったり、結局問題が解決していなかったり、そもそも途中経過報告だったり、何ならメモ書きみたいなものもあったりします。
であれば僕が出すアウトプットも必ずしもクオリティの高いものを出す必要はないと考えるようになりました。
もちろんクオリティをあげる努力は必要ですが、「クオリティの高さを追求するあまり結局アウトプットを出せなかった」なんてことになれば本末転倒です。
そんなわけである程度のクオリティになったらすぐアウトプットを出すようにしました。
ネタ被りは気にしない
何かしらのアウトプットのネタを見つけた際、すでに似たような内容のものがないか調べると結構な頻度で似たようなものが見つかります。
以前はすでにあるネタに関しては新たにアウトプットする必要ないと考えていたのですが、今はネタ被りでもアウトプットして問題ないと考えています。
例えば、ある不具合に対する対応策に関する記事が記事Aと記事Bの2つあるとします。(不具合の内容、対応策はどちらも同じ)
人によって記事Aの方がわかりやすいこともありますし、記事Aでは理解できなかったが記事Bで理解できたという人もいると思います。
「[不具合名] 対策」で調べたら記事Aはヒットするが記事Bはヒットしない。一方「[不具合名] 解消」で調べたら記事Aはヒットしないが記事Bがヒットする。こんなケースも考えられます。
したがって、全く同じ文章でない限りどちらもそれぞれ異なる価値のある記事と言えます。
そんなわけで、ネタ被りをしていても解説なり表現なりで自分なりの個性を出せそうなものであれば臆せずアウトプットすべきだと考えるようになりました。
ただし、あまりにもネタの内容がシンプルすぎて個性の出しどころがなさそうなものに関してはあきらめています(笑)
1回アウトプットを出してみると意外と大したことない
先日生まれて初めてZennで技術記事を公開しました。
最初は公開するのは緊張したのですが、2つ目3つ目の記事を公開するときはもう大して緊張していませんでした。
最初の1回目は確かにハードルが高いのですが、それ以降のハードルはかなり低くなります。人によっては最初以外はハードルがなくなるかもしれません(笑)
何かしらアウトプットを考えている人は、まず1回アウトプットを出してみることをおすすめします。
今後の目標
アウトプットは継続して出すことが大事だと思うので目標を立てます。ブログに書くことで達成しなきゃ感を高める狙いもあります(笑)
とはいえ難しすぎる目標を立てて挫折してしまっては意味がないので、「無理のないペースで続けられるけど、達成出来たらそれなりのアピールになる」くらいの絶妙な塩梅のもので行こうと思います。
具体的には以下のペースでアウトプットしていく予定です。
| アウトプットの内容 | 頻度 |
| ブログ | 月に2回 |
| 技術記事(Zenn) | 仕事がある月は1回 仕事がない月は2回 |
| SNS(X) | 日に1~3回 |
「もうちょっと頑張っても良いんじゃない?」と言われるかもしれませんが、まずはこれくらいの目標で行こうと思います。
しばらく続けてみて、もう少し頑張れそうなら頑張ります。
おわりに
アウトプットを出すことは、いままでやらなきゃやらなきゃと後回しにしてきたのですがようやく重い腰をあげて取り組むことにしました。
今後、この取り組みが功を制して「仕事が決まりやすくなった」「文章力があがった」みたいな成果が出てきたらあらためて記事にしたいと思います。
それまではちまちまアウトプットの量を積み上げていこうと思います。
もし僕と同じくなかなかアウトプットを出すことに躊躇してしまっている人は、これを機に一緒にアウトプットしてみませんか?
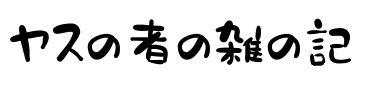
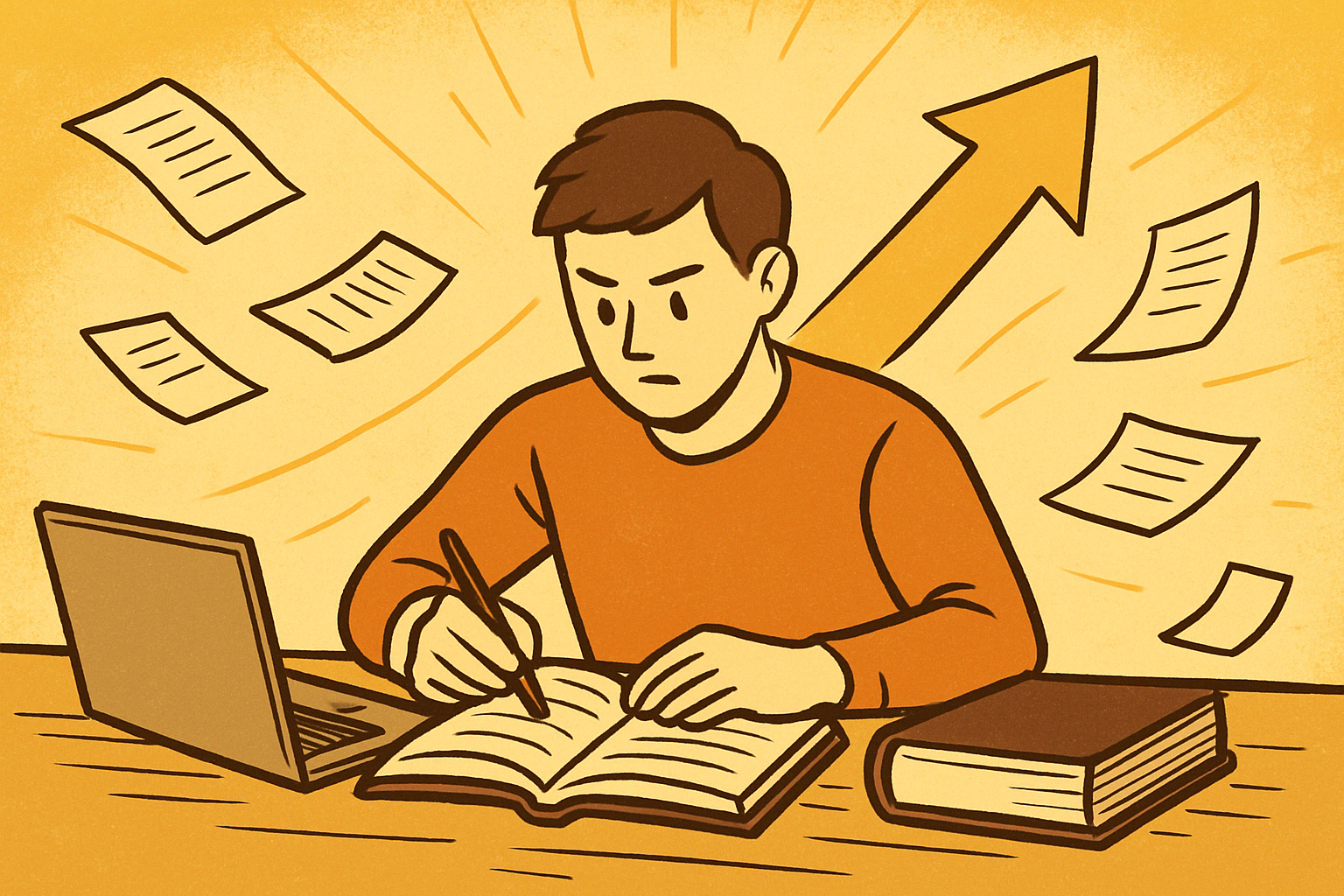
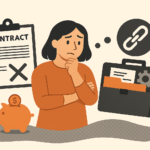
コメント