つい先日2024年度の確定申告を行いました。
確定申告は毎年2月15日から3月15日頃に行う、前年度の所得に対する所得税を計算して税務署に申告・納税する手続きのことです。2025年のように15日が休日の場合は翌月曜日が期限になったり、コロナ等の時は特定で4月15日まで期限が伸びたりすることもあります。
今参画している案件では、副業等で確定申告が必要なメンバーが多かったので、皆さん「めんどくさい」と言いながら確定申告していました(笑)
フリーランスになると税金や社会保険料の負担をすべて自分で管理・支払いする必要があります。
会社員からフリーランスになった場合は、今まで会社がやっていたそれらのことを自分でやることになるため、ギャップが激しいです。
僕もフリーランスになりたてのころはあれこれ調べながら納税していました。
そんなわけで今回はフリーランスエンジニアが意識するべき税金・社会保険料について解説していこうと思います。
なお、この記事はあなたに関係ある税金・社会保険料を完璧に過不足なく記載してある訳ではありません。あくまでも参考程度に留めておいてください。
意識せざるを得ない税金
所得税
所得税の定義はこちらです。
ざっくり説明すると、儲けにかかる国の税金です。
細かい計算式はややこしいので割愛しますが、大事なポイントは以下の通りです。
- 所得(儲け)が多いほど税率が上がる累進課税
- 経費の分は所得に含まれないので所得税がかからない
- 年金や保険料、ふるさと納税等は所得控除され所得税がかからない
経費とは仕事に使ったお金のことで、「通勤の交通費」「スキルアップ用の書籍代」等が該当します。リモートワーク等で自宅で仕事をする人の場合は、「仕事用のPC代」「仕事時間中の電気代」等も経費として扱うことができます。
何が経費として扱えるかは税理士の人でも色々な意見があるようです。僕の場合は自信をもって「○○の理由で仕事で利用しているものです」ときちんと説明できるもののみ経費にしています。
たまに勘違いしている人がいるらしいのですが、会社員の経費は会社が払うべきお金を一時的に会社員が肩代わりするため全額返ってきますが、フリーランスの経費は所得税の対象外になるだけで経費の額が返ってくるわけではありません。
所得控除は年金や保険料といった所得から差し引くことが認められているもののことです。ふるさと納税やiDeco、配偶者控除等の多岐にわたる項目があるのでしっかり活用するとけっこうな節税になります。
ここで説明しきれないほど種類があるので、気になった人はネットなりYoutubeなりで調べてみるのをおすすめします。
売上が多ければ多いほど納める税金は増えますが、経費や所得控除をうまく活用することで納める税金を減らすことができます。
ただし、経費や所得控除の額以上に税金が減ることはありません。例えば10万円を経費として計上したからといって所得税が10万円以上減ることにはなりません。
節税を意識するあまり、不要なものを買ったり過剰な生命保険に契約する等をしないよう気を付けてください。
予定納税
予定納税の定義はこちらです。
ざっくり説明すると、前年の所得税が一定額に達している場合に支払う必要がある今年度の所得税の先払いです。
「予定納税」という税金の種類があるわけではなく、所得税に該当するものではあるのですがちょっとややこしいので別カテゴリで解説します。
確定申告後、6月頃に予定納税額の通知書というものが届くことがあります。
基本的に所得税は確定申告の際に納付するのですが、納税額が一定以上ある場合は「今年も同じ納税額だとしたら、これくらいは払えると思うから先に払ってね」というのが予定納税です。
副業かつさほど納税額が多くないうちは予定納税が発生することは少ないと思いますが、フリーランスとして活動している場合はほぼ確実に予定納税が発生します。
ここで注意が必要なのが予定納税額は前年の納税額を基準に計算されるということです。
前年に急に売上があがって納税額が激増した場合は、当然予定納税も激増します。
今年も同じくらいの売上があがっていればまだなんとかなるかもしれませんが、今年は売上減だったりしたら予定納税はかなりの負担になります。
もちろん払いすぎた分は次回の確定申告時に還付(払いすぎた税金の払い戻し)が発生しますが、一時的にとは言え資金が減ってしまうのは状況によっては致命傷になりかねません。
「Youtuberやインフルエンサーが急にバズって大金を稼ぎ、翌年の予定納税が支払えず大変なことになる」なんてのはよく聞く話です。
住民税
住民税は住んでいる市区町村に納める地方税です。
前年の所得に対して一律10%の税率で課税されます。
確定申告後、大体5~6月頃に納付書が送られてきます。
納付は6月(第1期)、8月(第2期)、10月(第3期)、翌年1月(第4期)の4回に分けて支払います。(まとめて支払う事も可)
住んでいる地区町村によっては「QRコードを読み取って自宅で支払い」といったこともできたりします。
住民税の納付先は住民票の市区町村になります。
引っ越しをした場合は住民票の変更手続き(転出届、転入届)を忘れずに行いましょう。
消費税
消費税の定義はこちらです。
ざっくり説明すると、売上等で受け取った消費税から経費等で支払った消費税を差し引いた額を納税することになります。
フリーランスの場合は前々年度の課税売上が1000万を超えると納税義務が発生します。2024年度の消費税の場合は2022年度の売上が対象です。(課税売上=消費税が含まれている売上)
条件を満たしていない場合は免税事業者となり消費税を支払わなくてもよいです。(支払ってもよいです)
フリーランスエンジニアの場合、大抵の売上に消費税がかかる上に、経費は大して多くならないことが多いので差し引ける消費税は少ないです。
したがって、特に何もしてなければ100万円近く支払わなければいけなくなることもあります。
そこで大事なのが簡易課税制度の利用です。
課税売上が5000万円以下であれば利用でき、事業区分に応じたみなし仕入れ率を売り上げの消費税から差し引くことができます。
例えば売り上げの消費税が100万円だった場合、エンジニアは第5種事業に分類されみなし仕入れ率は50%なので納める消費税は以下のようになります。
100万円 ー (100万円 × みなし仕入れ率50%) = 50万円
大抵のフリーランスエンジニアは売上の50%も経費にしたりしないので、簡易課税制度を利用することでかなりの節税になるはずです。
簡易課税制度を利用するためには、その課税期間の前日までに申請が必要です。2024年度に簡易課税制度を利用したい場合は2023年12月31日までの申請が必要になります。
「消費税を払わなければいけないかも?」となった場合は早めに簡易課税制度の申込をしましょう。
また、消費税に関しても納税額が多いと中間納付が発生します。(消費税版の予定納税のようなものです)
注意事項は基本的に予定納税と同様です。ある程度の預金は確保しておきましょう。
個人事業税 ※業務内容による
個人事業税は法定業種(法律で定められている特定の業種)に課される地方税です。
法定業種外の業種あるいは所得が低いと課税対象外になります。
フリーランスエンジニアは基本的に個人事業税の対象外の業種として扱われることが多いです。少なくとも東京都内では課税対象外です。
ただし、住んでいる都道府県によっては「請負業」とみなされ課税対象となるケースもあるようです。
現住所ではどの業種に該当するかきちんと調べておき、「個人事業税の納付書が来たけどお金がない!」みたいな状況にならないよう注意しましょう。
意識せざるを得ない社会保険料
国民健康保険料
国民健康保険の定義はこちらです。
地方自治体ごとに運営されており、所得に応じて保険料が決まります。
大体年間所得に対して8~10%前後の保険料になることが多いです。(上限あり)
フリーランスになった場合、国民健康保険に加入する手続きが必要です。
加入手続きは市役所で行います。
今まで使っていた会社の健康保険等の資格がなくなった日が加入日になります。
加入日と加入手続きを行った日が空いている場合、その間の保険料も支払う必要があります。
フリーランスになって最初に支払額に驚くのがこの国民健康保険料だと思います。
所得にもよりますが、会社員時代の数倍になることも珍しくありません。
僕も妻に自分の支払っている保険料を伝えたら驚かれました(笑)
ただし、上限が設けられているので無限に支払いが増えるわけではないのでご安心ください。※所得税は上限がないので無限に支払いが増えます
また、国民健康保険組合に加入するという手もあります。
業種によって加入できる健康保険組合が異なるので、気になる人は「フリーランス エンジニア 健康保険組合」等で調べてみるとよいでしょう。
加入条件や手続き等がありますが、所得によっては支払額を数十万円減らすこともできます。
国民年金保険料
国民年金をもらうために支払う必要がある保険料です。
所得などに関係なく、支払額は月16980円(2025年3月時点)です。
年払いや前納で少し割引されます。
会社員の場合は厚生年金ですが、フリーランスの場合は国民年金に切り替わります。
こちらも国民健康保険同様に手続きが必要なので注意しましょう。
市役所または年金事務所で手続きが可能です。
国民年金保険料を払い忘れると、受給額が減ったり受給資格が喪失したりするので気を付けましょう。
たまに国民年金基金というものの案内も来たりしますが、これは国民年金とは別のものです。
国民年金は加入義務がありますが、国民年金基金は加入は任意です。
国民年金基金は年金の受給額を増やせる制度です。
ただ、個人的には国民年金基金を利用するより毎月の掛け金分資産運用していた方がメリットが多いと思っているので僕は加入していません。
税金・社会保険料の支払いスケジュール
税金・社会保険料の支払いスケジュールをまとめると以下の通りです。
| 税金・社会保険料 | 支払い時期 | 備考 |
| 所得税 | 翌年の3月15日まで | 確定申告後に納付。 休日の場合、翌月曜日が期限になる。 コロナ等で特例的に期限が伸びることもある。 |
| 予定納税(所得税) | 7月末、11月末 | 前年の所得税額から計算。 |
| 住民税 | 6月、8月、10月、翌年1月 | 4回に分けて納付。 まとめて支払うことも可能。 |
| 消費税 | 翌年の3月末まで | 前々年度の課税売上が1000万円以上あるいはインボイス事業者(消費税支払いを選択した事業者)が対象。 |
| 中間納付(消費税) | 年1回の場合は8月末頃 年3回の場合は5月末頃、8月末頃、11月末頃 | 前年の消費税額から計算。 額に応じて回数が異なる。 毎年期限が少し違うので注意。 |
| 個人事業税 | 8月末、11月末 | 業種・所得から計算。 エンジニアは対象外のことが多い。 |
| 国民健康保険料 | 6月から翌年3月まで毎月 | 4月と5月は対象外。 |
| 国民年金保険料 | 毎月 | 所得に関わらず固定額。 年払いや前納で割引あり。 |
この表を参考にある程度の資金は確保しておくようにしましょう。
大体の目安ですが年間の売上が800~1000万円くらいあるのであれば、常に最低でも50万円、可能なら100万円くらいを納付用の資金として確保しておけばなんとかなると思います。
特に予定納税や国民健康保険料は時期になるといきなりけっこうな金額の納付書が届くので心の準備をしておいてください(笑)
まとめ
フリーランスになると、税金も社会保険料もすべて自分で管理して支払う必要があります。
会社員の時はさほど意識していなかった負担が一気に目に見える形でのしかかってくるため、初年度は戸惑う人が多いでしょう。
今回紹介した税金・社会保険料を意識しておけば思わぬ出費に悩まされることもないでしょう。
特に予定納税や消費税の中間納付はあらかじめ知っていないととてもビビります。(体験談)
フリーランスになって収入UPに成功したからと言って預金0になるまで散財することはやめてください。常に急な出費が発生しても問題ないように資金を確保しておきましょう。
また最初にも述べましたが、この記事はあなたに関係ある税金・社会保険料を完璧に過不足なく記載してある訳ではありません。あくまでも参考程度に留めておいてください。
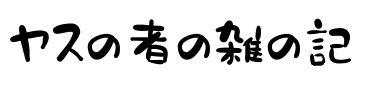


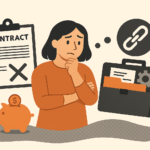
コメント