ソーシャルゲーム(以下、ソシャゲ)の開発現場では、聞きなれない用語が出てくることがあります。
かくいう僕もソシャゲ業界に入りたての頃はよくわからない単語に出くわすことが多かったです。
日本語であればまだなんとなく意味を予想できなくもないのですが、横文字だったりアルファベットの略称だったりするとお手上げ状態になりかねません。
特にアルファベットの略称は、他業界だと別の意味で使われている場合も多々あるのでややこしさに拍車をかけています。
そんなわけで今回はソシャゲ業界でよく使われる用語を解説していこうと思います。
これからソシャゲ業界に関わることになる人(なる予定の人)はぜひとも予習していってください。
ソシャゲ業界でよく使われる用語
KPI(Key Performance Indicator)
日本語で言うと重要業績評価指標です。
ソシャゲ業界に限らず使われるビジネス用語で、一般的には組織の目標の達成度合いを定量的に測定するための指標を表します。
ソシャゲ業界では、「とあるゲームを評価するための指標」的な意味合いで、ゲームの売上やユーザー数、継続率といった定量化(=数値化)できる指標の事を指します。
会社やプロジェクトによってどれをKPIとするかは変わりますが、売上やユーザー数は大抵のゲームでKPIとして設定されています。
KPIの数値が良ければ会社としても力を入れていきたいゲームとなるので、人員増加や大規模改修の工数確保が容易になったり、有名なIPとコラボできたり、会社によってはインセンティブがもらえることもあります。
逆にKPIの数値が悪ければサービス終了となります。
流石に1回や2回数値が多少悪かったとしても即サービス終了となることは少ないですが、何か月も数値が低迷している等だとサービス終了の可能性は大きくなります。
KPIの良し悪しとプランナーの評価は直結しているので、大抵のプランナーはKPIを気にしています。
「KPIを良くすることがプランナーの仕事」と言い切ってしまっても過言ではないかもしれません。(異論は受け付けます)
DAU/MAU(Daily Active Users/Monthly Active Users)
ゲームをプレイしたユーザー数です。
DAUは1日にゲームをプレイしたユーザー数、MAUは1か月にゲームをプレイしたユーザー数になります。
ユーザーの定着率やゲームの賑わいや規模を示す重要な指標で、よくKPIとしても用いられます。
僕はディーエーユー、エムエーユーと発音してますが、ダウ、マウと発音する人もいます。
組織として複数人で運用するゲームであれば、DAUは数百~数千人くらいは欲しいところです。
DAUが数万~数十万人くらいあるとだいぶ安泰あるいはめちゃくちゃ稼ぎ頭だったりすることが多いです。
単語としてはWAU(Weekly Active Users)というものもあるようですが、僕はあまり聞き馴染みがないのでソシャゲ業界ではあまり使われない単語かもしれないです。
逆にDAU/MAUは「知ってて当然だよね?」と言わんばかりにどのソシャゲ会社でも使われてます。
ちなみに過去にフリーランスとして参画したとあるゲームが、開発人数が数十人にも関わらずDAUが100行かないと聞いた時は「終わった…」と思いました。
事実、参画して1か月後にサービス終了が決まってしまい、僕自身もあっという間に契約終了となってしまった悲しい思い出があります(笑)
継続率、リテンション(Retention)
継続率とは、ゲームをインストールしたユーザーがどれくらい継続してプレイしているかを示す指標です。
会社やプロジェクトの文化によってはリテンションという言葉を使うこともあります。
「1日後(翌日)継続率」「7日後継続率」「30日後継続率」といったように、大体日数とセットで使われることが多いです。(僕は使ったことはありませんが、D1リテンション、D7リテンション、D30リテンションとも呼ぶそうです)
意味は字の通りで、基準となる日にゲームをインストールしたユーザーのうち、○日後にもプレイしているユーザーの割合を表します。
ざっくりとした定義は上記の通りですが、細かい計算方法は会社ごとにまちまちだったりします。
例えば「7日後継続率」を計算する際、基準日から7日間毎日プレイしたユーザーのみカウントする場合もあれば、基準日からちょうど7日目にプレイしていれば5日目にプレイしていなくてもカウントする場合もあります。
KPIとしてよく使われる継続率は「1日(翌日)後継続率」、「7日(1週間)後継続率」、「14日(2週間)後継続率」、「30日(1か月)後継続率」あたりです。
もちろん「2日後継続率」「25日後継続率」といった値もデータは取得していますが、僕が知る限り上記以外の日数の継続率が話題になることはなかったです。
LTV(Life Time Value)
日本語で言うと「生涯価値」です。
1人のユーザーがゲームをプレイする間にどれくらいの収益をもたらすかを示す指標です。
ソシャゲだと基本的に以下のような計算でLTVを求めます。
LTV = ゲームの総収益 ÷ ゲームの総ダウンロード数基本的に課金型のゲームほどLTVは高くなり、広告料で稼ぐカジュアルゲームはLTVは低くなります。
課金型にも関わらずLTVが低い場合はサービス終了に1歩近づきます。
LTVがわかるとダウンロード数増加に対する収益の増加具合がある程度予想できるので、CMやコラボといったダウンロード数を増加させる施策をやるかやらないかの判断の材料になります。
PU(Paying User, Paid User)
課金を行ったユーザー数を示す指標です。
基本的にこの値が多ければ多いほど売上が安定します。
PUR(PU Rate)
DAUやMAUといったゲームをプレイしたユーザー数のうち、PUの割合です。
PURが高いほど、ゲーム内の課金への誘導がうまく機能していると言えます。
ARPU(Average Revenue Per User)
日本語で「ユーザー1人あたりの平均売上」です。
僕はエーアールピーユーと発音してますが、アープと発音する人もいます。
売上をユーザー数で割った値です。
以下のように計算します。
1日のARPU = 1日の売上 ÷ DAU
1か月のARPU = 1か月の売上 ÷ MAU主に課金を促す施策がユーザーに効果があったかどうかを判断するために使われたりします。
例えばとあるガチャ施策を行った際、ARPUがあがっていればユーザーの需要の高い商品を出せたと言えますし、ARPUが下がっていればユーザーの需要の低い商品を出してしまったと言えます。
ARPPU(Average Revenue Per Paid User)
日本語で「課金ユーザー1人あたりの平均売上」です。
僕はエーアールピーピーユーと発音してますが、アップと発音する人もいます。
ARPUとほぼ同じような計算ですが、割る値が異なります。
具体的には以下のように計算します。
1日のARPPU = 1日の売上 ÷ 1日のPU
1か月のARPPU = 1か月の売上 ÷ 1か月のPU一見するとARPUと同じく高ければ高いほど良いような気もしますが、実はそうでもありません。
ARPPUが高いということは、売上に対する課金しているユーザー(PU)1人あたりの依存が大きいこととなり売上の不安定さにつながります。
例えば、1か月の売上が1000万円かつARPPUが1万円のゲームAと、1か月の売上が1000万円かつARPPUが100万円のゲームBがあったとします。次の月も同じような売り上げが期待できる状況でしたが、ゲームAもゲームBも課金ユーザー(PU)がたまたま1人減ったとします。すると、ゲームAは売上が999万円とさほど痛手ではありませんが、ゲームBは売上が900万円となりなかなかのダメージとなってしまいます。
じゃあARPPUが低い方が良いのか?と思われるかもしれませんが、低い場合は低い場合でたくさんの課金ユーザー(PU)を集めなければいけないので、それはそれで大変です。
高すぎず低すぎずの程よい値を追い求めなければいけないというなかなか難しい指標だったりします。
マネタイズ(Monetize)
ゲームが売上を出すための方法のことです。
ソシャゲの場合はガチャや広告といったものが主なマネタイズになります。
企業が出すようなボリュームが多いゲームはガチャ、個人が出すようなボリュームが少ないゲームは広告がマネタイズとなっていることが多いです。
もちろん上記以外にもソシャゲのマネタイズはあります。
固定の商品を購入可能にしたり、ログインボーナスを通常より豪華にするサブスクリプション的なものを用意する等があったりします。
ただ日本で出すゲームであれば、やはりガチャか広告が強いです。
ガチャとは違うマネタイズに挑戦したゲームに関わったことがありますが、あまり思ったように売上があがらずに結局ガチャに方針転換したりしていました。
SAP(Social Application Provider)
ソーシャルアプリを開発・提供している事業者を指します。
ソシャゲ業界で使われる場合は、基本的にソシャゲ会社のことを指します。
エスエーピー、サップ等と発音します。
単語の意味自体は上記の通りなのですが、ややこしいのが他業界だと別の意味で使われることが多い単語だということです。
有名なERPパッケージ(企業の経営資源を統合的に管理するシステム)の名前にもSAPというものがあります。
特にBtoBの企業で働いていた人からするとERPパッケージのSAPの方がメジャーだと思います。
僕ももともとBtoBの企業で働いていたので、ソシャゲ会社に転職したての頃は「SAPは~」とかの話を聞くたびに「なんでソシャゲ会社でERPパッケージの話してるんだろうか…?」と疑問に感じたものです。
エンドコンテンツ(End Contents)
ゲームの開発側が用意する、ゲームの最終的なやりこみ要素のことです。
裏ボスや難易度選択の最上位といったものが該当します。
あくまでもゲームの開発側が機能として用意しているやりこみ要素の事を指すので、RTA(リアルタイムアタック)や縛りプレイといったユーザー側が自ら遊び方を工夫してやりこむものはエンドコンテンツとは言いません。※ゲームの機能としてタイムアタックや縛りが提供されている場合は別
ソシャゲ業界でエンドコンテンツというと、基本的にはめちゃくちゃゲームをやりこんでいたり、かなりの額を課金したりしているユーザー、いわゆる上位ユーザー向けのやりこみ要素を指します。
あなたが無課金あるいは微課金で遊んでいるソシャゲで「こんな強い敵勝てねーよ!」って思うようなやたらと難易度の高い敵に出くわしたことがあるのではないでしょうか?ずばりそれです。
エンドコンテンツは上位ユーザーがゲームに飽きてしまわないように用意されるものなので、通常のユーザーがクリアすることを想定していません。(通常ユーザーはエンドコンテンツ以外を楽しんでもらうよう設計されています)
個人的にはやりすぎなくらい難易度を高くしても問題ないと考えています。
上位ユーザーは下手すると開発側よりゲームに精通していたりするので、「けっこう難しくしたのにあっさりクリアされてしまった」なんてことは珍しくありません。
僕もしょっちゅうそんな現場に出くわしました。
まとめ
以上、他業界or未経験からソシャゲ業界に来た時に聞きなれない用語の解説でした。
今回はどの現場でも出てくるような用語をまとめました。
もし需要がありそうならもう少しマイナーな用語についても解説していこうかと思います。
ソシャゲ業界は、リーダー以外のエンジニアでもゲームの売上や運営方針についての話を聞く機会がけっこう多いです。
今回解説した用語をあらかじめ知っておくことで、より内容が理解しやすくなるはずです。
くれぐれも「よくわからない用語でよくわからない会話をしている…」と思考停止になってしまわないよう気を付けましょう。
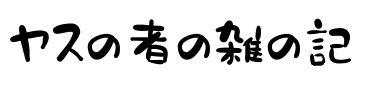
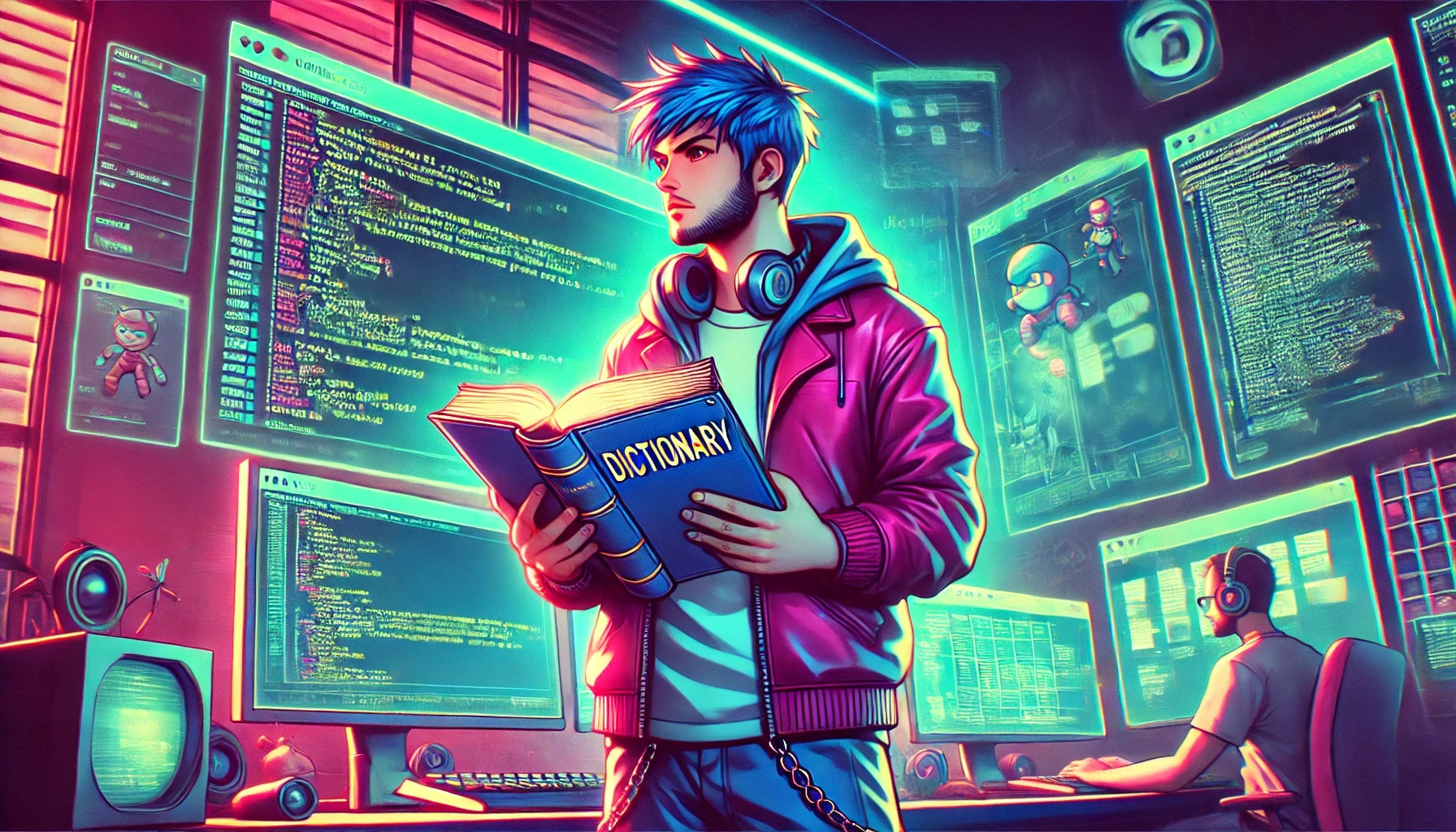


コメント